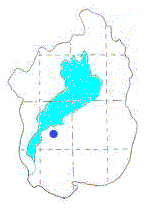
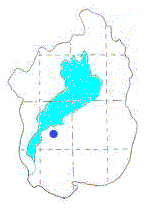
1.はじめに 近江には勧請縄(かんじょうなわ)を吊るす風習があります。 神社の鳥居などに掛けられる注連縄(しめなわ)に似ていますが、少し違います。 私が生まれ育った群馬では見かけた記憶がありません。近江の地に移り住んでみると、色 んな珍しい風習を見かけますが、勧請縄もそのひとつです。 先ずは勧請縄の一例をご覧ください。これは我が家から1km弱の場所、JR野洲駅か ら北東に2km足らずの場所にあります。(写真は2012年1月撮影)←我が家の近くの勧請縄(1) ↓
勧請縄(1)では小枝を円形状に結んだ輪を縄の中央に吊るし、その左右の上部に御幣 を立てています。勧請縄(2)では複数の輪の飾りが吊るされています。 勧請縄(1)は古い民家の集落の入口に当たる位置に建てられています。 勧請縄(2)の向こうには集落がありませんので、手前の方向にある集落の入口に当たる 位置なのかも知れません。(現在は昔の道路と違った位置に道路が整備されています) 勧請縄(1)と(2)は100m程の近い場所にあります。
←我が家の近くの勧請縄(2) ↓
2.勧請縄(かんじょうなわ)と注連縄(しめなわ)の違い 勧請縄とはどういう意味なのでしょうか。 「勧請」の語を辞書で調べてみると、いくつかの意味があるようですが、「神仏の来臨や 神託を請い願うこと」という説明がありました。古来から祀ってきた八百万(やおよろず) の神に、遅れて現れた仏教用語を当てるのは不適切ではないかと思います。が、それはと もかくとして、何のために神に祈るのかと言えば、村の安全や五穀豊穣のためだろうと思 います。 勧請縄と注連縄の違いとは、私の(推測を交えた)理解では、次のようなことかと思い ます。 ・大きさ :一般に勧請縄は注連縄よりも大きい(出雲大社などは巨大な注連縄を飾る) ・飾る場所:勧請縄は集落の出入り口の道路か神社の参道に飾られるが、個人の家には飾 られない。注連縄は神社、巨石や巨木など神のおわす場所や、個人の家にも 飾られるので、多くの人が目にすることが多い。 ・縄の材料:一般には勧請縄も注連縄も稲わらが使われる。(神道では注連縄は古来から 麻が使われたようである) ・飾り付け:勧請縄は注連縄よりも飾り付けが大きく、複雑、かつ地域で異なる。 注連縄は飾り付けが質素でどの地域でもあまり違わない。 ・飾る時期:勧請縄も注連縄も新年を迎える準備として年末に飾られる。勧請縄は翌年末 まで吊られている。注連縄は正月が過ぎると外される(どんど焼きで燃やさ れたりする)ことが一般的だが、伊勢市内では一年中飾られている。 3.勧請縄の例 それでは、野洲市内の勧請縄をもう少し眺めてみましょう。 JR野洲駅の南西約1km圏内に、行事神社と新川神社があります。 冒頭でご紹介した勧請縄(1)と(2)は集落の出入口に飾られたものですが、両神社 の勧請縄(3)と(4)は神社の参道に飾られています。(写真は2012年1月撮影) まず行事神社(ぎょうじじんじゃ)を見てみましょう。 参道の入口にある石の鳥居には注連縄が掛けられています。その鳥居の少し奥の参道に勧 請縄が吊るされています。中央には縦横斜めに4本の割り竹が結ばれ、中央に木の札が結 ばれています。その左右に多数の紙垂(しで?)と小枝が吊るされています。よく見ると、 左側には6個、右側には7個吊るされています。通常は左右に6個づつですが、この年は うるう年(2012年)なので右側は7個とされています。
←行事神社の勧請縄(3) ↓
新川神社(しんかわじんじゃ)も注連縄の掛けられた鳥居の奥に(写真では分かりにく いかも知れませんが)勧請縄が吊るされています。 ここの勧請縄は十字に結んだ細い竹に割り竹が円形に結ばれています。行事神社では勧請 縄の下を通行できる高さに吊るされていますが、新川神社では通行を妨げる位の低い位置 に吊るされています。
←新川神社の勧請縄(4) ↓
4.勧請縄の分布 村落の境界に稲わらや草などを吊るす習慣は日本の各地に残っているようです。 特に多いのは近畿地方で、滋賀県、奈良県、京都府、三重県などの各地にわたっています。 滋賀県では県の南東部に集中しており、東近江市を筆頭に、我が野洲市、近江八幡市、 甲賀市、大津市などが多いようです。意外なことに、県の北部と西部では少ないようです。 その理由は不明ですが、私は次のように推測しています。 つまり、県の南東部には近江平野が拡がっており、沢山の集落ができているため、集落毎 に境界を明示させようという意識が強くなったのではないでしょうか。ちなみに、関東平 野では家が分散しているのに対して、近江平野では集落毎に家が密集している傾向があり ます。 余談ですが、滋賀県の南東部にいわゆる近江平野が拡がっているのは、琵琶湖が移動し たためだろうと思います。琵琶湖は約400万年余り前に三重県の北部、現滋賀県に隣接 する伊賀市に生まれ、次第に北上して約100万年前に現在の位置まで移動してきた世界 で三番目に古い古代湖だそうです。 5.勧請縄の歴史 勧請縄はいつ頃から飾られてきたのでしょうか。 国立国会図書館デジタルコレクションなどで絵図を探してみました。 「近江名所図会」の老蘇の杜(おいそのもり)に勧請縄と思われる描写がありました。 図左下の鳥居を入った参道に勧請縄らしき綱が張られています。 近江名所図会が刊行されたのは今から200年ほど前の1815年(文化12年)だそう です。
←近江名所図会(部分) ↓一遍上人絵図(部分)
「一遍上人絵図」(一遍聖繪)にもそれらしき描写がありました。 堀で囲まれた大きな屋敷の入口に勧請縄と思しき綱が張られています。中央に四角の板が 吊るされ、その左右に4本と3本、木の枝のようなものが吊るされています。 旅ごろも 木の根かやの根 いづくにか 身の捨られぬ 処あるべき と詠んだ一遍上人は、その生涯をかけて全国を遊行し、念仏の教えを弘めたそうです。 一遍上人絵図はおよそ700年前の1299年(正安元年)に発行されたそうです。 勧請縄の祀りがいつ頃から行われてきたのかは明らかではないようです。 私の推測では平安時代よりもずっと前から、少なくとも千年以上は続いているのではない かと思いますが、どうでしょうか。 6.おわりに 本稿では野洲市の我が家の近くで見られる勧請縄をご紹介しました。 私が興味深いと感じたのは、せいぜい2,3km以内の狭い地域の勧請縄(1)〜(4) が、縄を張って飾りを吊るすという点では共通しているものの、飾り方は極端に言えば統 一されておらず、いわば独創的だということでした。 野洲に限らず、ネットで各地の勧請縄を見てみると、実に色々な飾り方があります。 注連縄は勧請縄よりも形状が共通化されている感じがします。注連縄は家庭でも飾られる ので、近年は遊び感覚で様々な形状の注連縄が作られたりしていますが、伝統的な注連縄 は縄に紙垂を下げる点では共通しています。 地域によって飾り方が違うということは、地域住民の結束力を高めることが意識されて きたのかも知れません。その団結意識が何世代、何十世代もの長い間、祀りを継続させて きたのだろうと思います。 ただ、現代の生活環境を考えると、この伝統を継続させることは難しい問題もあります。 例えば、縄を作るには餅米の稲わらが必要のようですが、機械刈りではなく手刈りが必要 などの手間が要ります。人々の伝統を守ろうとする意識の変化も気になるところです。 是非、長く伝統を継承していただきたいものです。 ご参考までに、近江の珍しい祀りの例です。 ・野洲市:山神祭 ・日野町:芋くらべ祭 (散策:2012年1月上旬 脱稿:2021年12月30日) 参照資料: 1.勧請縄 2.注連縄 3.各地の勧請縄の画像 4.注連縄の画像 5.国立国会図書館デジタルコレクション - 一遍聖繪 第八巻 6.近江名所図会 老蘇の杜 ------------------------------------------------------------------ この稿のトップへ 報告書メニューへ トップページへ